「目的」を上手に伝えるために♪
話しが相手にうまく届かない理由
こんにちは!ちょこ札幌事務所スタッフです。
今回は「目的を上手に伝える為に♪」をテーマに、ちょこ札幌のチャットレディの皆さんにお話していこうと思います。
これはチャットレディのお仕事をしていく上でも非常に役立つ内容となっておりますので、是非最後まで読んでいってくださいね☆
話には、いろいろな目的があります。
どんな目的の話でも、「わからせる」ということがつきまとってきます。
つまり、説明の部分がはいっているということです。
ところが、この説明がうまくいかないことがあります。
どこに問題があるのでしょう。
ちょこ札幌のチャットレディの皆さんはわかりますか?
説明とは「ある事実をことばに置き換えてかえて話す」ということです。
説明することが苦手という人は多いと思います。
なぜこんなにも難しいのでしょうか。
そこには様々な理由があるからです。

〇使うことばの意味が人によって違う
ことばは絶対の意味を持ちません。
時とともに変わり、場所とともに変わります。たとえば、関西系のことばで「なおす」。
それは、関東系の「修理する」とか「あらためる」。
などという意味以外に「片づける」「もとにもどす」「しまう」があります。
若い人は「私、頭にきたわ」と自分でいいます。
昔は、本人が「頭にきた」とはいわなかったのです。
心に病を持った人などをさして、他人がいったことばです。
また、ことばは恣意的(しいてき)に受け止められます。
話されたことばの意味が一致することは、悲観的にいったら「ない」ということです。

〇「好感の感情」で話の受け止め方が変わってくる
話しては聞き手に、聞き手は話し手に対して、好き、嫌いがあった場合。
その好悪によって、話の内容の受け止め方が違うのです。好きな人からいわれたことと、嫌いな人からいわれたこと。
それは、同じことばでも受け取り方が違います。
人は自分の感情によって色眼鏡で他人の話を受け止めているということになります。〇「事実のとらえ方」が人によって違う
「酒は百薬の長」と思い、こよなく愛する人がいます。
逆に「酒を口にすると体調が悪くなる」と敬遠する人もいます。タバコを吸っている女性を見て「かっこいい」と思う人もいます。
ですが、タバコを吸っている女性は苦手という人もいます。人によって事実のとらえ方や価値観は違います。
これらのことをよくわきまえておかないと、理解の障害になります。また、話し手自身が説明しようとする内容を十分につかんでいるのか?
それを、たしかめてみる必要があります。
案外、わかっているつもりのことが、わかっていないということは多いものです。
ちょこ札幌のチャットレディの皆さんは、自分の腕にはめている時計の文字盤がどんなものなのか。
見ないではっきりわかりますか。
こうしたこと一つをとってみても、人間の理解というものが、いかにあいまいなものか。
そのことがわかると思います。

ふだんちょこ札幌の皆さん自身が身につけているものでさえそうなのです。
自分でわかっていなければ、わからせようがありません。そして、相手がどの程度わかっているのか?
どこが不十分で、どこがわかっていないのか?
そこをつかんで話さないと、説明が過不足になります。わかりやすい説明をするにはどうしたらいいのでしょう。
いくつかのポイントがあります。☆わかりやすいことばを使う
☆具体的に話す
☆比較してわかってもらう
説明が上手にできる人はしっかり物事を理解している人です。
自分の判断でわかっていると思い説明をしたときに恥をかくこともありえます。
わからないことがあれば自分が納得いくような理解力も必要になります。
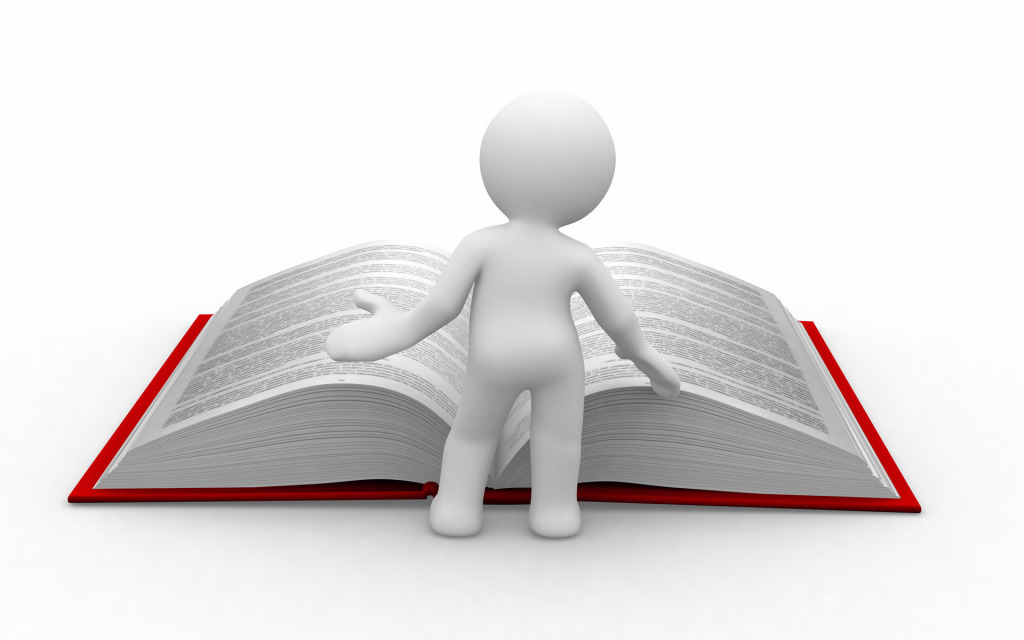
わかないことがあったらすぐに調べてみる。
それが習慣づけば、逆に説明する側になったとき知的な女性(チャットレディ)と印象づけられます。
また、受ける側になったときもすんなり頭に入っていくのではないでしょうか。
会話がスムーズにいくということは異性関係だけに関らず人間関係もスムーズに行くのです♪
勿論これはチャットレディのお仕事においても同じことが言えますね☆
ちょこ札幌の皆さんも、今回お伝えした内容をしっかりと頭に入れて、より一層愛されるチャットレディさんになっていきましょう☆
ちょこ札幌の事務所スタッフの中にはチャットレディ経験者も多数在籍しておりますので、何かわからない事や不安な事があればお気軽にご相談くださいね♪













